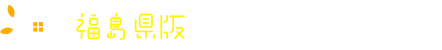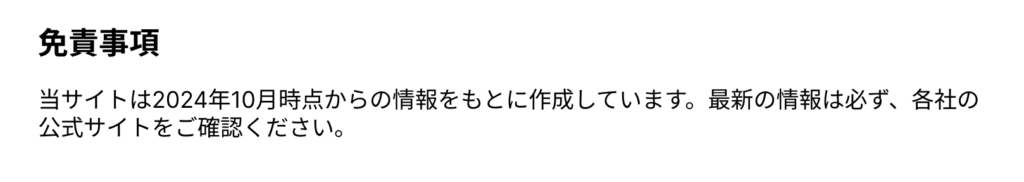夫婦が離婚する場合、不動産をどうするかという問題は必ずと言っていいほど発生します。特に住宅ローンが残っている不動産については、離婚に伴ってどう対処するべきか分からない方も多いでしょう。
住宅ローンについては、離婚後に不動産を売却するか、どちらか一方が住み続けるかで対応が異なります。住宅ローンの残債がある場合の対処方法を知っておくことで、離婚に伴う不動産の問題を素早く解決し、手続きを始めることが可能となるでしょう。
この記事では、離婚後の住宅ローンの対処方法やケース別の売却方法、支払い方法について解説していきます。
また、以下の記事では、福島県で早期売却におすすめの会社も紹介しているので、参考にしてください。
離婚後の住宅ローンを対処する方法
離婚する際に住宅ローンが残る不動産については、以下の2つの対処方法があります。
売却もしくはどちらかが住み続けるというのは、離婚に伴う不動産の扱い方として代表的なものです。それぞれの対処方法について解説していきます。
売却する
離婚後に夫婦で暮らしていた不動産を売却することで、ローン残高を一括返済し、財産分与のトラブルを回避しやすくなります。お互いに別の居住地が確保されている場合は、売却が選択肢になるでしょう。
売却を検討する際は、不動産会社への相談が重要になるため、早期に査定を依頼し、市場価格の把握から始めましょう。売却時期や価格設定を慎重に見極められるかどうかで、手続きのスムーズさが左右されます。
離婚協議中に売却を進める場合、双方の合意が必要となるため、引き渡し時期についても慎重な計画が求められます。仲介なのか買取なのかなど、売却については夫婦間で協議した上で結論を出す必要があるでしょう。
離婚後も住み続ける
離婚後もどちらかが住宅に住み続ける場合、どちらか一方が住宅ローンの支払い責任を引き継ぐ必要があります。通常、住宅の名義人とローンの契約者が一致していることが重要ですが、離婚時には名義変更やローンの借り換えが求められることもあります。
金融機関の審査に通ることで単独名義への切り替えが可能ですが、収入状況や返済能力の確認が行われるため、事前の準備が不可欠です。
名義変更が難しい場合には、ローン返済義務を共同のままにする選択肢もありますが、将来的なトラブルの原因となる可能性があるため注意が必要です。
売却する場合のケース別手法
離婚後に住宅ローンが残る住宅を売却する場合、以下のようなケースが想定されます。
それぞれのケースにおいて最適な売却方法は異なるため、ケース別の手法を見ていきましょう。
ケース①アンダーローン
アンダーローンとは、ローン残高が売却価格よりも少ない状態を指し、不動産売却によって得た資金で住宅ローンを完済することが可能です。このケースでは売却後に借金が残らないため、比較的スムーズな取引が期待できます。
売却後の資金の分配については、離婚協議で取り決めが必要になります。財産分与の割合は話し合いまたは家庭裁判所の調停で決定されます。売却益が発生する場合には譲渡所得税が発生するため、税務面での確認も欠かせません。
ケース②オーバーローン
ローン残高が売却価格を上回るケースは、オーバーローンと言い、アンダーローンの逆の状態を指します。このケースでは売却だけでローンを完済できないため、不足分を補わないと売却できません。
オーバーローンでの売却にあたっては、残債の処理方法を確認することが重要です。預貯金を追加したり任意売却を採用するといった対応をすれば、オーバーローンでも不動産を売却できます。ただし、貯金を使う場合は夫婦間で協議しなければいけません。
ケース③連帯保証
住宅ローンにおける連帯保証とは、債務者と同等の返済責任を負う制度です。離婚しても連帯保証人としての責務は自動的には解除されず、債務者がローン返済を滞った場合には保証人が返済義務を引き継ぎます。
アンダーローンの場合、売却手続きが比較的スムーズに進む可能性があります。この場合、売却後にローンを完済することで連帯保証人の責務も解消されるため、財産分与や生活設計に集中できるでしょう。
一方オーバーローンの場合、連帯保証人としての責務が続きます。例えば債務者である夫が返済を滞った場合、離婚後でも妻が残債を支払う義務を負います。残債の支払いリスクを避けるには、金融機関と交渉し、任意売却の承認を得るのが有効です。
ケース④連帯債務
連帯債務とは、複数の債務者がそれぞれ全額の返済義務を負う仕組みを指します。夫が主債務者、妻が連帯債務者という形で夫婦でローンを組むケースが多く、家の名義も共有になることが一般的です。
アンダーローンであれば、夫婦双方の同意を得て売却手続きを進めることで責務の解消ができます。ただし、売却代金の分配方法は財産分与の対象となります。
オーバーローンでは売却金額が残債に届かないため、家を売却してもローンが残る問題が発生します。この場合、主債務者・連帯債務者のいずれかが返済を続ける義務を負うため、片方が支払いを滞ると、もう一方が全額負担するリスクがあります。
ケース⑤ペアローン
ペアローンは、夫婦それぞれが個別に住宅ローン契約を結び、互いに連帯保証人となる方法です。この場合家の名義は夫婦共有となり、双方に対して平等な権利と責任が発生します。
アンダーローンの場合、家の売却代金で双方のローンを完済できるため、名義人である夫婦が合意すれば、売却手続きがスムーズに進みます。一方、オーバーローンでは夫婦双方が引き続き債務者および連帯保証人としての責務を負うことになるでしょう。
住み続ける場合の住宅ローン支払い方法
離婚後もどちらかが住宅に住み続ける場合、住宅ローンの支払いを継続しなければいけません。この場合、以下のような方法で支払うのが一般的です。
それぞれの支払い方法について解説していきます。
方法1:住宅ローンの名義を変更する
住宅ローンの名義を変更することで、家に住み続ける側が住宅ローンの名義人となり、残りのローンを引き継ぐことが可能です。
名義変更により、元配偶者の返済責任は解消されるため、双方にとってメリットがある場合もあります。ただし、名義変更の手続きには登記の変更手数料や司法書士への依頼費用が発生するため、事前の費用確認が重要です。
方法2:離婚前の名義人が支払いを継続する
名義変更を行わない場合、家に住む人が誰かに関わらず、離婚前の名義人が支払いを継続します。名義変更の審査が厳しい場合や、収入面での不安がある場合に検討されます。
この方法を選ぶ際は、ローン返済者と住み続ける側との間で、返済費用や生活費の負担分担の取り決めが必要です。住宅ローン契約そのものは名義人が負担するため、返済が滞った場合は信用情報への影響が避けられません。
そのため、離婚前の名義人が支払うことで問題ないか夫婦間で決める必要があります。具体的な金銭負担について明確にしないと、トラブルに発展するかもしれません。
方法3:家賃として名義人に支払う
家賃として名義人に支払う方法とは、住宅ローンの名義人が引き続きローン返済を行い、住み続ける側が名義人に家賃相当額を支払うケースです。名義変更をせず、住み続ける側が金銭的負担を請け負うため、トラブルに発展しにくくなります。
この方法を採用する場合、名義人に支払う家賃の設定が重要です。住宅ローンの月々の返済額や固定資産税、維持管理費などを考慮して、双方が納得する金額を決める必要があります。
住み続ける側は住宅ローンの返済義務を直接負うわけではありませんが、支払いが滞ると名義人の信用に影響を与えるため、返済状況の管理も重要になります。ローン名義人が家賃収入を得る形になるため、課税面での確認も必要です。
離婚に伴う不動産売却なら東海住宅株式会社がおすすめ

| 項目 | 詳細 |
| 会社名 | 東海住宅株式会社 |
| 住所 | 本社:〒276-0032 千葉県八千代市八千代台東1-2-11 福島支店:〒960-8055 福島県福島市野田町5-2-50 郡山支店:〒963-8034 福島県郡山市島1-11-1 |
| 電話番号 | 本社:0120-333-419 福島支店:0120-180-182 郡山支店:0120-703-708 |
| 公式サイト | https://www.10kai.co.jp/file/tokaisale/area/fukushima.php |
東海住宅株式会社は、不動産の売買から賃貸管理、リフォーム事業を展開する総合不動産会社です。千葉県・福島県・宮城県・栃木県に根ざしたサービスを通じて、長年にわたり信頼と実績を築いてきました。
多様なニーズに応える柔軟な提案力と、専門知識を生かしたきめ細やかなサポートが東海住宅の強みです。不動産の査定から契約手続き、引き渡しに至るまで、すべてのプロセスで安心できるサポート体制を整えています。離婚に伴う住宅ローンについても、スタッフが相談に乗り、適切な売却方法を提案します。
福島県以外にも多くの拠点があるほか、大手に並ぶほどの実績があるため、県外の買い替え客も優先して紹介してもらえる点などもおすすめのポイントです。該当エリアでの不動産売却を検討している方は、東海住宅をチェックしてみてください。
以下の記事では、東海住宅の特徴や口コミ、売却事例などをさらに詳しく解説していますので、気になる方はぜひ一度チェックしてみてください。
まとめ
離婚に伴い、住宅ローンの返済方法が変更する必要が生じるかもしれません。売却するか、夫婦のどちらかが住み続けるかによって、売却方法や支払い方法が異なります。
住宅ローンについてはトラブルに発展しやすい側面があるため、以下の点が重要です。
- 夫婦間で徹底的に協議する
- 住宅の名義人が誰か確認する
- 離婚後その家をどうするか夫婦で共有されている
住宅の取り扱いについて夫婦間で合意されていれば、支払いや売却に関するトラブルは発生しにくくなるでしょう。双方が納得できる形で、住宅ローンの対処・住宅の維持もしくは売却を進めてください。